現在、日本で暮らす「外国ルーツの子」、あるいは「外国につながる子ども」達の多くは、さまざまな困難を抱えています。
コチラの記事『「外国につながる子ども」のシビアな現状~子どもの日本語は難しい!』では、主に学校生活での彼らの苦労、主に学習言語について取り上げました。
でも深刻な問題はこれだけではありません。
この記事では、私が見聞きした彼らのプライベートでの困難について取り上げます。
ダブルリミテッドバイリンガル

ダブルリミテッドバイリンガル…Double Limited Bilingual…
って、聞いたことがあるでしょうか?
バイリンガルだけれども、両言語ともある程度のところまでしか伸びておらず、年齢相応のレベルに到達していない。
という状況を指す言葉です。
日本にいる「外国につながる子ども」にも、この状態の子ども達がいます。(もちろん、そうならない子もたくさんいますが)
彼らは、学校など、家の外では日本語を使います。使わざるをえません。
それに伴い、第一言語である母語を忘れていく場合があります(来日年齢にもよりますが)。
もちろん自宅では親と母語で話し続けるでしょう。
でも親以外の人と母語を話す機会がない、母語で読んだり書いたりという機会もほとんどない、と言う場合、母語をバランスよく年齢相応に伸ばしていくことは難しくなります。
第二言語である日本語はどうかというと、最初のうちは苦労しつつも、日常会話はできるようになっていきます。(子どもが低年齢であればあるほど、順応性は高いです)
ところが・・・。
周囲の日本人(日本語母語話者の子ども達)は、年齢を重ねるにつれ、どんどん難解な言葉を理解しそれらを使って抽象的な概念まで考えながら、複雑なことを話したり読んだり書いたりできるようになっていきます。
が、元々日本語が第二言語であるというハンディを背負っている彼らにとってはそう簡単にはいきません。
周囲の母語話者の子達との差は開いていきます。
もし友人間で疎外感を味わったり自己肯定感が低くなったりすると、不登校になることもあります。
しかもそこでぶつかる困難な問題を自宅で親に相談することもできません。
母語でも日本語でも、言葉を駆使して十分に詳しく状況を説明し親に理解させることが、できないからです。
・・・ダブルリミテッドバイリンガルの子達は、非常に難しい状況に置かれていることになります。
親の現状

子どものこのような状況を知ってか知らずか、彼らの親は仕事に忙しいなどの事情もあり、日本語を本格的に勉強できない人が多いです。
私は自分が関わった子どもたちの親向けに、自治体の無料の日本語教室を紹介していました。ところがあまり通おうとはしれくれませんでした。
(通ってくれた人もいましたが、なかなか長く続けるのは難しかったようです。)
しかも、多くの親は、大きな誤解をしているように感じました。
子どもは放っておいてもどんどん日本語の力を伸ばし、すぐに不自由なく操れるようになる、と(悪気なく)信じているのだと思います。
母語のように。
違うのに。
そうなると、どうなるか?
・・・子どもがヤングケアラ―化します。(各親子で程度の差はかなりあると思いますが)
ヤングケアラ―化
ヤングケアラーというのは、家庭内のさまざまな事情により、本来大人が担うべき家事(病人や高齢者・小さな弟妹の世話から、料理洗濯などの日常的な家事まで)を担わざるをえない子どもたちのことです。
日本語を話せない親をもつ子もヤングケアラ―と言えるのではないかと思います。
子どもは学校から親への連絡も自分が理解して親に伝えなければなりません。
プリントなども訳さなければなりません。
親と先生の二者面談も無理ですから、自分が通訳として入らなければなりません。
子どもが少し大きくなれば、役所の手続き、病院の診察、アパートの不動産屋や近所の人とのやり取りに至るまで、あらゆる場面で通訳の役割を求められます。
が、なにしろ彼らもリミテッドなのです。日本語も、母語も。
彼らの負担がどれほどのものかを考えるとめまいがしてきそうです。
親子関係は良好なのに・・・

でも、概して彼らの親子関係は良好です。
とても絆が強いです。
ところが、ダブルリミテッドバイリンガルの悲劇は、ここにもあります。
母語しか話せない親と、母語が中途半端な状態になってしまった子。
仲良しの親子なのに、その親子間でも表面的な会話しかできなくなるのです。
(語彙が少ないということは、言葉を使ってあれこれ思考を深めることができない、そして抽象的な、複雑な内容を話し合うことも困難だ、ということです。)
私が関わった子の1人は、親と夕ご飯は一緒に食べるけれども、あまり話すことはないと言っていました・・・。「お母さんはどうせ日本語分からないから」と言っていました。
子どもにとっては、親といろいろなことを話すことで精神的に安定したり、成長したりする部分がたくさんあるはずなのに、その機会が徐々に失われていくのです。
すぐそばにいるのに・・・。
おわりに
今、私は「子どもの日本語」から離れていますが、関わっていた頃にもっと何かできたのかなあなんて考えることがあります。
これからでも関われる機会があれば、少しでも何かできたらいいなと思っています。
自分の意志と関係なく日本に来るという選択肢しかなかった子達を、その地域の人たちで温かく見守れる社会でありたいなと思います。
・・・と同時に、もっともっと国や自治体からの手厚い支援があればいいなと、切に思います!
それが結果的に日本のより良い未来を守るための投資にもなるわけですから。

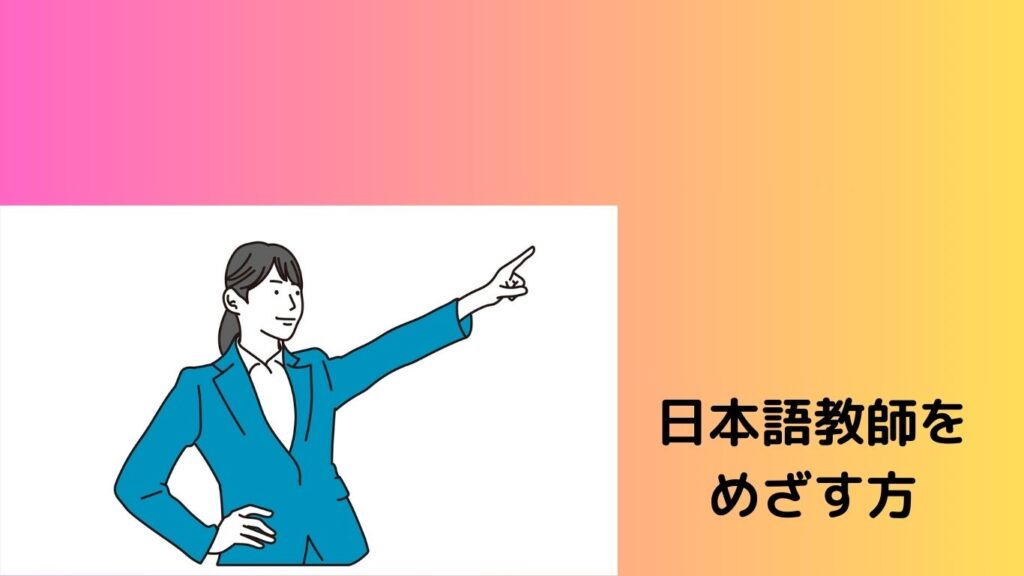
コメント