この記事は、「やさしい日本語」についてまだあまり知らない人に向けたものです。
【※既にご存じの方は、コチラの記事『やさしい日本語に書き直してみよう!練習問題×3題』で実際に作ってみませんか?】
この記事で分かるのは、以下のことです。
・「やさしい日本語」とは何か。
・「やさしい日本語」の歴史。
・「やさしい日本語」を作るときの基本的なルール。
(この記事の下の方にも、「やさしい日本語」を作る練習問題的なものを一つ用意しています。)
「やさしい日本語」とは?
日本語が初級レベルの外国の方にも分かりやすいよう、使う語彙や文の形等を工夫した、「簡単な日本語」のことです。
「やさしい」はひらがなで書かれることが多いですが、「易しい」= 簡単な、という意味と同時に、「優しい」= 配慮のある・思いやりのある、という意味でもあると思います。
それは実は、外国人だけでなく日本人の小さな子供たちやさまざまな障害のある人など、あらゆる人にとって分かりやすい、ユニバーサルデザインの言語だと言えるでしょう。

「やさしい日本語」の歴史は、まだ浅いが、深い。
最近じわじわと、場所によっては急速に広まってきた『やさしい日本語』。
1995年の阪神・姫路大震災で多くの外国人の方が犠牲となり、その後の避難生活でも大変な思いをされた外国人被災者が多数いたことがきっかけで必要性が言われるようになりまました。
阪神・淡路大震災の後も、度重なる台風や2011年の東日本大震災など、日本で大きな災害が起きるたびに「やさしい日本語」の注目度は上がってきました。
(弘前大学の佐藤和之名誉教授の発信が有名です。東日本大震災後、佐藤先生のゼミのメンバーは24時間体制で「やさしい日本語」による情報発信を行ったそうです)
そして2024年のお正月。
能登地方を襲った大地震の際には、ついにNHK総合テレビのアナウンサーまでもが一部「やさしい日本語」を使用していました。
(そのことについては、こちらの記事『能登の地震と、やさしい日本語と、NHKのアナウンサーと…』にまとめています)

どこか特別な場所で意識の高い人たちだけの間で使われるのではなく、
広く一般の人々が視聴する公共放送で使われたことは、とても意義深いことだと思います。
「やさしい日本語」のルール × 8
では、「やさしい日本語」はどうやって作ればいいでしょう。
ルールがはっきりと決まっているわけではありませんが、一般的には以下のようなことが言われています。
① 一文に一つの内容。
句点(「。」)で切れるのが文です。一つの文の中にたくさんの情報を入れないようにしましょう。
基本的には一文につき、一つの内容にします。
② できるだけ、短い文。ただし省略や、あいまいな表現を避ける。
①を心がければ自然とそうなると思いますが、文は構造が単純で短いほど分かりやすいです。
読点(「、」)をたくさん使ってダラダラと続く文は非常に分かりにくいです。
とはいえ省略は避けましょう。日本人同士なら前提として分かることでも、外国の人には分かりにくいことが多々あります。
また、あいまいな表現も避けましょう。擬音語や擬態語、オノマトペ。
たとえば「グラグラ揺れる」とか「ササっとやる」とか……日本人ならすぐにイメージができて便利な言葉ですが、外国人にはなかなか伝わりません。
誰が読んでも(聞いても)はっきりと意味が限定できることが重要です。
③ 難しい漢字と、漢語やカタカナの外来語はできるだけ避けて、分かりやすい和語を使う。
漢字や、漢字の組み合わせでできる漢語は、中国人には分かりやすいですが、それ以外の国の人にはとても難しい表記です。
カタカナの外来語も、欧米の人が聞くとびっくりするような使い方・表記のものがたくさんあります。誤解されることもあるので可能なら避けましょう。
もちろん、日本語にはその言い方しかないという場合は避けられませんが、その言葉を実際に使うときは、意図した意味で伝わっているかどうかに十分気を付ける必要があります。
できるだけ、日本人の小さな子どもにも正確に通じるような和語、つまり日本固有の語彙を使いましょう。
④ シンプルな文型を使う。
「みんなの日本語」という日本語教育業界にいる人ならだれでも知っている日本語のテキストがあります。
この初級レベルのテキストで勉強するぐらいの文型を使いたいものです。
本屋さんの日本語教育関連コーナーには必ず置いてあるメジャーな本です。
ぜひ一度手に取って、初級レベルの日本語がどんなものかをチェックしてみてください。
⑤ 文は「です」「ます」調にする。常体(「~だ」「~である」)を使わない。
外国人が日本語を勉強する際、「~です」「~ます」の形から覚える人が多いです。
日本語の初級テキストにも「~です」「~ます」の形が先に出てきますから、初級レベルの外国人学習者にも分かりやすいです。
⑥ なくても困らない情報は、入れない。
「あってもいいけれど、なくても別に大丈夫。」という情報は、思い切って削りましょう。
内容が多岐にわたり複雑になると、肝心な最重要情報がぼやけてしまいます。
一字一句そのまま簡単な言葉に置き換えるのではなく、必要な情報のみを取り出して、やさしい日本語に変換するのがポイントです。
⑦ (書き言葉の場合)ひらがなの分かち書きにする。もし漢字を使うなら、ふりがなをふる。
分かち書きというのは、読むときに分かりやすいよう、適宜ブランクを入れた書き方です。
たとえば、『わたしは きょう、 あさの 6じに おきました。』のように、文節(…中学校で習ったと思いますが、覚えていますか??? ~ね、で区切ることのできる部分を文節と言います。懐かしいですね!)ごとにブランクを入れます。
この書き方は、日本の小学校一年生の国語教科書でも採用されています。
また、もし漢字を使う場合は、ふりがなをふりましょう。
⑧ (話す場合)ゆっくり、はっきり話す。
話す場合は、聞き取りやすいようにゆっくり、はっきりと話しましょう。
早口だとなかなか伝わりません。
おまけ:見た目が外国人でも、やたらと英語で話しかけない。
外国人でも、英語を知らない人は、たくさんいます。
特にアジアから来ている人々は、英語が苦手な人も多いです。
ヨーロッパや中南米から来ている人たちの中にも、英語を話さない人は多いです。
ですから、もし英語で話したいなら、まず相手が英語を話す人かどうかを確認しましょう。
その上で、話す言語を決めます。
英語を話さない人なら、やさしい日本語を使うようにしましょう。
「やさしい日本語」にしてみよう!
では、ここで「やさしい日本語」への変換練習をしてみましょう!
下の日本語の文は、某駅のホームにあった張り紙を若干アレンジしたものです。
これをやさしい日本語に直してみてください。
『当駅では、平日朝六時から九時までこの付近に止まる車両は女性専用車両となりますので、男性のご利用はご遠慮くださいますようお願いいたします。』
⇩
⇩
⇩
解答例。
『月(げつ)ようび ~ 金(きん)ようびの 朝(あさ)6時(じ) ~ 9時 : 男(おとこ)の人は ここで 電車(でんしゃ)に 乗(の)ることが できません。女(おんな)の人だけ 乗(の)ることが できます。』
元の文には、「当駅」・「平日」・「この付近」・「車両」・「女性専用車両」・「男性」・「ご利用」・「ご遠慮くださいますよう」、…難しい日本語がいっぱいあります。
そこから、なくても困らない情報を削り、言葉を簡単なものに置き換え、一番大切な情報をしっかり伝える文になっていると思います。※本当は漢字の後ろに( )より、漢字の下にふりがながあった方が見た目もきれいで、より分かりやすいと思います…
(もちろん、冒頭に書いたように「やさしい日本語」にはただ一つの決まったルールというものは存在しませんから、人によって少しずつ違う文になると思います。)
以上をふまえて、もし、もっと練習をしてみたいという方は、コチラの記事『やさしい日本語に書き直してみよう!練習問題×3題』からどうぞ!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
少子高齢化の進む日本では、今後ますます外国の方の力を借りる場面が多くなると思います。
ということは、ご近所さんや同僚にも外国人が増えていくということです。
彼らが皆、日本語の勉強に熱心ですぐに日本語上級者になる…ということは、ありません。
地方自治体やさまざまな機関が発行する案内、パンフレット等には、外国人住民・利用者への配慮として「やさしい日本語」を使用したものも増えてきました。
隣人として、お互いに寄り添い合える工夫の一つとして、「易しい日本語」「優しい日本語」がますます広まっていくことを願っています。

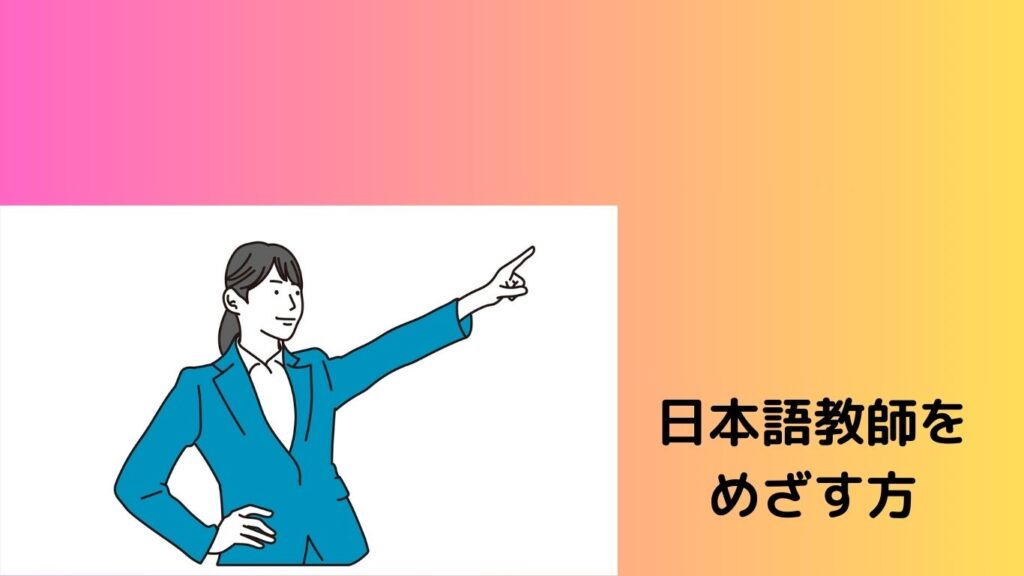
コメント