「模擬授業」・・・できれば避けたい・・・でも避けては通れない・・・そんな風に思いませんか?
私は今でも自分がやると思うと変な汗をかきます。
特に日本語教師の資格を日本語教育能力試験だけで取得した方(実は私もです)は、
採用試験本番で初めて経験する関門ですから、なおのこと緊張すると思います。
420時間の養成講座出身の方は、講座で何度も実習をされると聞きます。
が、やはり採用試験本番は緊張されるのではないでしょうか…
そこで今回は、「敵(?)を知る」という意味で、
日本語学校採用試験の「模擬授業」ではどのようなことがチェックされているのかを
シェアしたいと思います。
※私自身がかつて面接担当をしていた頃の覚え書きです。
一例としてお読みください。

模擬授業で気を付けたいこと×10。
①事前の授業準備は十分にする
②当日の準備も十分にする
③説明を分かりやすくする
④板書を理解しやすくする
⑤学生への指示の出し方は明確にする
⑥メリハリをつける
⑦学生への目配りを忘れない
⑧想定外のことに臨機応変に対応する
⑨時間配分を適切にする
⑩声、表情を明るくする
以下に具体的に記していきます。
①事前の授業準備は十分か
明らかに事前の準備が不足していると分かる模擬授業は
大きく減点されてしまいます。
文型の分析はしっかりやっておきましょう。

調べるだけでなく、ストンと納得できるまで自分自身でもよく考えておくと安心です。
模擬授業中に質問が飛んできても、焦らずに済みます。
教案は提出しない場合でも、綿密なものを作っておいた方が安心です。
特に緊張しがちな人は。
そしてもちろん、家で何度も練習しておきましょう。
なお、当日教室で何を使えるのかは事前に確認しておきましょう。
たとえばUSBメモリを持ちこみたい場合、
教室でノートパソコンやプロジェクター、スクリーンなどが使えるのかは
聞いておく必要があります。
②当日の準備は十分か
模擬授業に絵カードなどを持ち込む人がいます。
ところがいざ使おうとすると目当てのものが見当たらない…
順番通りに並べておかないとアタフタと探すはめになります。
そういうところは細かく減点されると思いますので気を付けましょう。
模擬授業の開始前に確認できる時間がない場合もありますから、
これは家を出る前の段階での準備です。
そして教卓の上に何をどのように置いて始めるか、
シミュレーションをしておくといいでしょう。
③説明は分かりやすいか
当然ですが、教師は学生に分かりやすい説明をしなくてはなりません。
何より大事な教師の仕事です。
特に初級レベルの模擬授業では、何が既習で何がそうでないのかを頭にしっかり入れて臨みましょう。
語彙や文型のコントロールが甘いと、話が学生に通じません。
・・・日本語学校で学生から
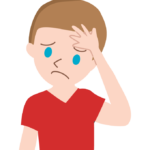
○○先生の授業は、分かりません・・・
というクレームが入るのは本当に困ります。
ですからそういう可能性のある人は、いくら人手不足でも不採用になってしまいます。
相手のレベルに合わせ、その人たちに無理なく伝わるように話しましょう。
また話すスピードにも気を付けましょう。
緊張して早口になる人もいるので要注意です。
なお、いろいろと調べてきたことを全て学生に伝えようとするのはNGです。
自分の授業準備としては大事なことですが、
学生には必要十分な情報量で伝えるようにしましょう。
あまり細かいことを伝えすぎると学生は混乱します。
以前模擬授業で、「こんなことまで調べました!」とアピールしたかったのか、
情報をてんこ盛りにする人に会ったことがあります。
が、そういう授業は学生は分かりづらいだろうなあと思いました。
④板書の仕方は適切か
書く場所があちこちに飛んだり、
ポイントが分かりにくかったり、
マーカーの色をその時の気分で選んでしまっていて統一感がなかったり・・・は、
良くないですね。

マーカーの色は、たとえば基本は黒で、ポイントは赤で、接続は青で…
といったように決めておくといいでしょう。
もちろん字が雑なのもNGです。
きれいでなくても、せめて丁寧に書きましょう。
ちなみに、板書をするときに完全に学生に背を向けてしまって、
しかも黙って書くことに集中してしまう人がいます。
これも学生そっちのけに見えるので、良くないと思います。
板書についてはこちらの記事にまとめていますので、よろしければお読みください。
⑤指示の出し方が明確か
学生が「今、何をやるべきか」をしっかり理解できるような指示を出しましょう。
説明をしているのか、
何かをやるよう指示しているのか、
学生に発言させようとしているのか、
そういうことがハッキリと分かるような話し方が大切です。
もちろん模擬授業のとき学生役をしているのは多くの場合日本語教師ですから、
理解してくれます。
が、明確でないと感じたら容赦なく理解できないふりをするはずです。
(…僭越ながら私もそうしていましたから!)
⑥メリハリがあるか
ずっと同じ単調な感じで授業が続くと、学生は眠くなります。
全体の流れの中に、学生がワクワクするようなポイントを作りましょう。
たとえばパターンプラクティスで代入練習や拡張練習をするようなときに、
学生が興味を持って引き込まれるようなおもしろさを入れ込むと気分転換になります。
学生役の教師は、
「実際にこの先生が教壇に立ったらどんな授業になるのか?」
をイメージしながら模擬授業を観察しています。
学生が楽しくなるような演出を考えながら教案を作るといいと思います。
⑦学生への目配りができているか
模擬授業を計画(教案)通りにうまく進めることに気が行きすぎると、
「次に自分は何を言うのか、するのか」を必死に頭で考えてしまい、
学生(役の教師)に目配りができなくなることがあります。

授業はライブなので、
自分のシナリオ通りに進まないことも当然あります。
学生がちゃんと自分の授業についてきているか、
理解しているか?
それは学生をしっかり見ていなければ分かりません。
⑧想定外のことに臨機応変に対応できるか
学校では、想定外のことが起きます。
地震などもありますが、
日常ちょくちょく起きる教師にとっての想定外といえば、
学生からの質問です!
まったく考えていなかったような質問がとんでくることは、
日本語学校の「あるある」です。
そういう時の対応を見るために、
ちょっと意地悪な質問をする学生役の先生もいます。
その場で必死に頭を回転させても答えが分からない場合は、
明るく素直に謝って「次の授業までの先生の宿題」にしてしまいましょう。
その場しのぎで誤ったことを答えてしまうよりは、よほどいいと思います。
⑨時間配分は適切か
模擬授業は、事前に何分でと指定されます。
その中で指示された内容を無理なく終わらせなければなりません。
時間配分はしっかり考えて進めましょう。
時計やスマホ(タイムウオッチ機能にしておくといいです)を使って
何度も練習しておきましょう。

実際の模擬授業のときも教卓に置いておくといいですよ。
ときどき、準備してきたことを全部やろうとして時間が足りなくなる人がいます。
また、上記のように学生役の先生から思わぬ質問が飛んできたりして、
想定していたように授業が進まない場合もありますが、
焦らずにいきましょう。
⑩声、表情は明るいか
教師は、教室ではできるだけ明るい雰囲気であるほうがいいと思います。
表情や声も大事です。緊張するかもしれませんが、
深呼吸して、明るい顔・明るい声でいきましょう。
教師が楽しそうな方が、学生も楽しいはずです。
(声の大きさもポイントです!)
模擬授業が終わったら
模擬授業と面接は同日に行われることが多いですが、
どちらが先かは学校によると思います。
私が面接を担当した2校では、面接の方が後でした。
私自身が採用試験を受けた側としてはどちらも経験したことがありますが、
あまりうまくいかなかった模擬授業の後に面接があると、
嫌で嫌で仕方なかったです。
「どうせ落ちるのに!」と思いながら
受け答えしていました。
・・・とはいえ、
自分では全然ダメだったと思っていても採用されることはありますし、
もし不採用だったとしても、
次の学校に行くための面接練習にはなります。
そういう気持ちで前向きに受けておきましょう!
何事も貴重な経験になります!
なお、事前に一度、自分の授業を録画録音してみると気づきが多いのでおススメです。

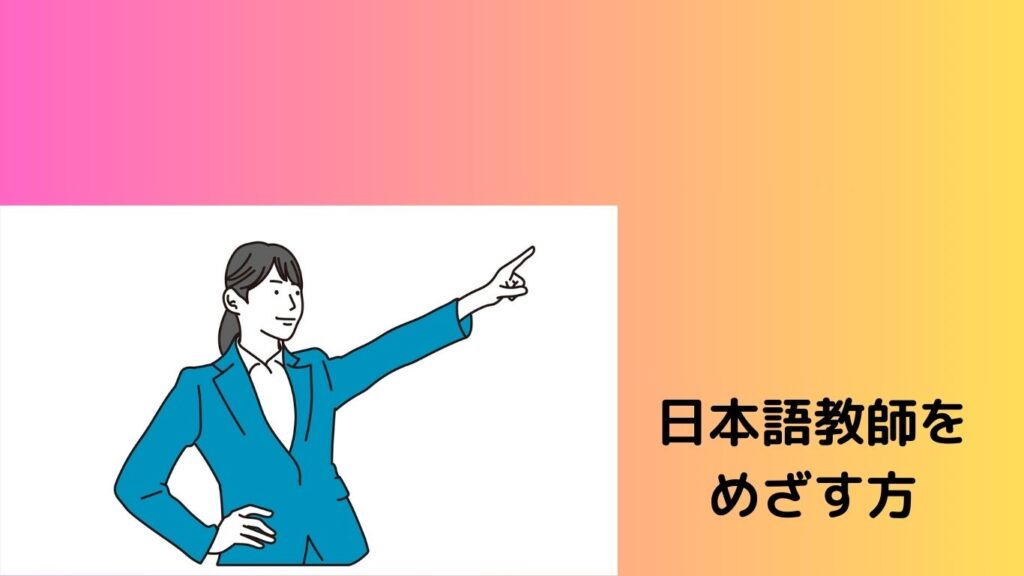
コメント