日本語学校の学生が卒業後に進学するのは、大学(や大学院)や専門学校。
そこに入るために必要なのは学校独自の「入学試験」(日本語の試験や面接試験)を突破することだけではありません。
前提として、日本語能力試験(JLPT)、そして大学の場合は日本留学試験(EJU)の受験が必須とされることが多くあります。
日本語学校の進学クラスでも必然的に、JLPTに合格し、留学試験で高得点を取るための指導をしていくことになります。
私も担当しているのですが・・・・・モヤモヤ。
「モヤモヤ」その1:JLPTそのものへの疑問
これは以前の記事(『日本語能力試験(JLPT)にまつわる「どうして?」四つ』)でも触れたことですが、
そもそもJLPTはコミュニケーション力を測るテストとしては不適切だと思っています。
なにしろ会話やスピーキングのテストがないのですから。
また、作文のテストもありません。
要するに「産出」つまり「表現」をすることの能力は正しく測れないのです。
でも、イマドキの大学や専門学校は、昔とは違います。
ただ本を読み、先生の話を理解してノートを取る受け身の「授業」ばかりではありません。
文科省も「アクティブラーニング」や「主体性をもって多様な人々と協力して学ぶ」ことを重視し、高等教育にもそれを求めています。
・・・これ、乱暴かもしれませんがうんと簡単に言えば、
「みんなで一生懸命調べて、考えて、たくさん話し合ってね。受け身じゃだめだよ!」
ってことではないでしょうか?

それをする学校に入ろうとする人たちの日本語能力を、JPLTで本当に適切に評価できるのでしょうか?
・・・日本の大学には、漢字圏の学生が押し寄せています。
彼らには、JLPTやEJUで高得点を取るために必要な「読み」に利があるのですから、
当然の結果です。
そのこと自体が悪いというつもりは毛頭ありません。
(読み書きだって大切な能力ですからね)
が、大学や専門学校が理想的な授業をしていく上で入学者に求める能力は、
それだけではないはず。
もっと多様な能力の測り方をして、多様な人々を大学に迎えられるような方法を導入する必要はないのでしょうか???
その方が学校も活性化すると思います。
「モヤモヤ」その2:テクニック重視教育への疑問
JLPTやEJUはほとんどがマークシートの選択問題です。(EJUには記述問題もありますが)
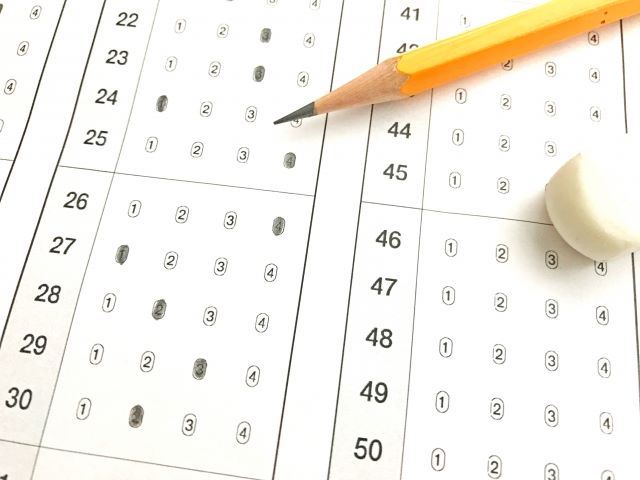
こういう問題を制限時間内で素早く処理していくためには、ある程度のテクニックが必要になります。
特に読解問題などは、最初からじっくり読んで全体を理解して正答を探す・・・という正攻法だと時間が足りなくなってしまいます。
そこで対策授業ではそのためのテクニックを伝授していくことになります。
先生によっては・・・
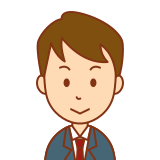
本文なんか読まなくても選択肢を読めばだいたい正解は分かりますよ!
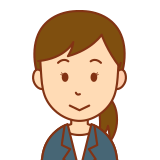
筆者の主張は必ず最終段落にありますから、最も言いたいことを問われたら、そこだけ読めばいいですよ!
なんて授業中に豪語したりするようです。
・・・なんだか空しくなります。
JLPTに合格するためだけの授業、EJUで高得点を取るためだけの授業。
これでは本当の意味で「読解力を伸ばす」授業にはなりません。
母語ならまだ仕方ないかなと思える部分もあるのですが、
彼らは外国語としての日本語を、まだまだ向上させていかなければならない大切な時期です。
進学先で充実した学びを得るためにも。
それなのに本当にこんな対策授業を日本語学校でしていてもいいのだろうか?
・・・と思うのですが、でも、彼らが進学のためにそれを望んでいるのも事実。
これを変えるためには、JLPTやEJUの中身を変えてもらうしかありません。
モヤモヤしつつも・・・
私は日本語教師です。
学生(つまりお客様)が望むなら、そういうテクニックも伝授しなければなりません。
・・・日本語学校も文科省の認定校になることですし、
Can doシラバスに変わりつつある今、
思い切ってJLPTやEJUの中身も刷新してくれないかな~・・・
と、夢を見ながら、私は明日からもある程度のテクニックを伝える授業をしていくことになるのでしょう。😞
(でも、その結果学生が合格したり高得点になれば、私も嬉しいのですが・・・複雑・・・)


コメント